最近の生成アートトレンドとデザイン業務への応用

ここ数年で急速に進化した「生成AI」。MidjourneyやAdobe Fireflyなど、誰でも手軽に画像を作れるツールが一般化しつつあります。
一方で「AIで作った画像って実際の仕事に使えるの?」と思う方も多いのではないでしょうか。
今回は、技術の紹介や解説…というよりも
最近の生成アートのトレンドをざっくりと紹介しながら、デザイナーとしてどう向き合うか?デザイナーの業務にどう生かせるか?を私なりにライトにまとめてみようと思います。
目次
トレンド①:AIによる“質感表現”の進化
AI生成の画像は、少し前まで下記のような「不自然な手」や「ぼやけた質感」が課題でした。

しかし2024年以降の生成モデルでは、特に素材感・照明・反射などのリアリティが格段に向上しています。

たとえばMidjourney v6では、金属や木材などの質感も非常に自然に再現できます。
この進化により「素材撮影の代替」や「イメージボード作成」の段階でAIを活用するケースが増えています。
トレンド②:現実×AIの“ハイブリッド制作”

最近のプロの現場では、「AI生成だけで完結させる」のではなく、AIで作った素材をベースに加工・合成して使うケースが増えています。
たとえば:
- 背景をAIで作成 → 人物や商品写真を合成して自然に仕上げる
- 構図案をAIに出して、IllustratorやPhotoshopで清書
- 色味やトーンをAI生成で決めて、最終調整を手作業で
このように、AIは「デザインを置き換えるもの」ではなく、発想を広げる相棒として使われるようになっています。
トレンド③:AIらしさを“デザイン表現”として活かす

生成アートの世界では、あえてAI特有の歪みや幻想的な質感を活かしたビジュアルも人気です。
「リアルさ」だけでなく、「AIっぽさ」を一つのデザインスタイルとして使う流れが生まれています。
特にSNSや広告バナーでは、少し違和感のある構図が“目を引くビジュアル”になることも。
「人が作れない不完全さ」を逆手に取る発想が、今のトレンドを支えています。
実務での活用例
では実際に、デザイン業務ではどう取り入れると良いのでしょうか?
一般的に初心者でも試しやすいと思われる活用例は下記の通り。
ラフ案出しに
頭の中のイメージを短時間で可視化できる。方向性を決める初期段階に便利です。
背景素材として
Webデザインやバナー制作では、AI生成の抽象背景が効果的です。トーン調整すれば商用利用にもなじみます。
プレゼン資料・社内提案に
“雰囲気が伝わる”ビジュアルをAIで即出力すれば、クライアントや上司との打ち合わせもスムーズ。
商品開発時の参考資料として
新商品開発時において、商品の画像に合わせた自然な背景イメージを生成し組み合わせる事で、よりリアルに商品の利用シーンがシミュレーションできる開発資料が用意できます。
AI活用は発想の【助け】として取り入れる
あくまで個人的見解ですが、AIツールを使いこなすポイントは「AIに100%完成を求めない」ことではないかと思っています。
最初のラフやインスピレーションをAIに任せ、最後の仕上げや表現の精度をデザイナー自身がコントロールするのが理想です。
AIが生み出す偶然性やスピード感を、デザインの「第一歩」として使えば、
作業効率とクリエイティブの両立がしやすくなります。
生成AIはまだ発展途上のツールですが、すでにデザイン現場の強力な味方になりつつあります。
「AIで作る」ではなく、「AIと一緒に作る」という意識が、これからのデザイン業務に重要になっていきそうです。
ちなみに弊社の運営する通販サイトでも、ページデザイン・広告デザインの作成や
新製品開発における参考資料としてなど、あらゆる場面でAI生成画像を積極的に活用しています。
こうして作られたサイトとは…?が気になる方は是非、下記バナーより確認してみてください!
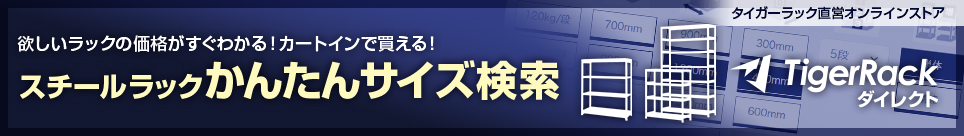
このカテゴリの最新記事
2025.01.17
2025.11.20
2025.01.09
2025.03.06










